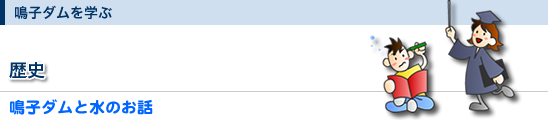
昭和32年に鳴子ダムができるまでの涌谷は、大雨が降ると水害が起きて被害を受け、農作業に水が必要な時期になっても水が来ないので春に田植えができませんでした。だから、我々が若い頃は、水はないものと決めていました。水は、利用しない。利用できない。本当に水が必要な春になっても、涌谷には水がないのです。
その頃、涌谷町内の田んぼには6月10日頃にならないと水が上がりませんでした。今は、6月10日だと稲がえらい成長して心配ないんですけど、当時はそうではありませんでした。
そんな時、涌谷の人はどうしたかというと・・・水をもらいに、大堰のある岩出山まで行っていました。それは、年中行事になっていたのです。それほど水がないんです、ここには。水をもらうために、議員さんや、役場の職員、みんなそろって上流の町や村に頭を下げて頭を下げて「田んぼにかける水をください!」とお願いしに行くわけですよ。
その頃、上流の方ではどんなふうになっているかというと、鳴子はもう田植えが終わって苗が根付いて少しこう伸び上がって、じゃばらで田んぼをかましてガラガラとほぐしている。岩出山は、ちょうど田植えをしていて早い人はじゃばらをしている。古川も、田植えを始めた頃。小牛田はしろかきをしてる。
涌谷の人は、だまって何もしない!。水がないから・・・だから、水をもらいに行く。上流から下流に来るにしたがってだんだんだんだん水がなくなっていくんですから、小牛田が最後に水を上げると江合川にはもう水がないんです。涌谷には、田んぼを潤して排水として出てきた水、一回使用した水が少し流れて来る。でも、それは一回使用したやつですからね。雨上がりには町と町が話し合いをしてね、上流の町から順番に「じゃあここまで!」と田んぼに水を入れていく。
そして、下流の涌谷は「これくらいは流してください!」という。
上流では、水位が「ここまで!」を越えた時に、江合川へいくらか流してやるというものでした。だから、涌谷の人達は、「水がほしい!雨がほしい!」と神さまを拝みに行っていたのね。
雨を降らせてくれる水の神さまがいる水神峠にね。
そんな昭和8年に、田尻川に水が来ない涌谷の町側、左岸の我々のいるところに水がひとたりとも来なかった。日照りの年で、田尻川自体が水がないので田尻の人は木の板を上まであげて水をこぼしてくれない。田尻ではみんな田んぼで番をしていてね、全部自分の方の田んぼさ水流して人寄せないようにしてんだ。だから、下流の涌谷の人はその木の板をやくしに(壊しに)行ったの。あの土を掘るのに使うやつを持ってね、夜中に出かけでった。「行ってぐっからね!」と、みんなに挨拶をしてね。
でも、暗い田んぼの中だから思ったより壊せない。それでも、がんばって壊した。だから壊される方は、死活問題。半鐘を鳴らして、半鐘を鳴らすのは、今サイレンを鳴らすのと同じだったの。番をしていた連中は、水泥棒が来たと鐘を叩き下の方まで来て「何さ来だ?」って怒鳴って、大喧嘩をしでた。壊した方はこっち向いて逃げろとなって、必死に逃げた。それでね、逃げるときに下流の涌谷の方と上流の方と分かれた。
下流に逃げた人は皆捕まってだ。上流に逃げるやつは涌谷のやつじゃないから・・・といわれて追いかけられなかったのね。だから、早く涌谷に帰って来たのは、涌谷と反対方向の上さ逃げた人たちだったのね。これを水戦争っていってました。
いろいろなことを思い出しても、昔の涌谷の人達が、どれだけ苦労していたかというのは、言葉ではいいあらわせません。