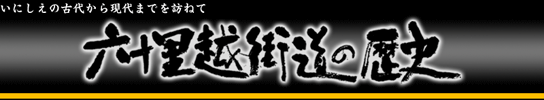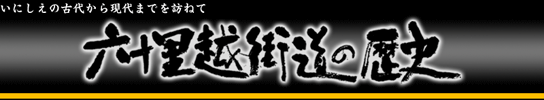江戸時代に入って三山詣は盛んに行なわれた。六十里越街道の要地志津村村明細書には、慶応三年(1867) 卯年までは毎年20,000人以上の止宿泊人があってこのうち1,400人は峠を越える旅人で残りが湯殿山の参詣者であった。延享二年(1745)丑年の月山通過行者は38,000人。四年11,000人と記してある。羽黒に登って下山するか湯殿山を参詣して帰る者が多く、月山を経由す る行者は少なかったようで、大部分は六十里越街道からまず手向へ向い、そこから羽黒山に登り、また六十里越街 道を引き返し、湯殿山に参詣していた。 六十里越街道を通る旅人の便を図るために、松根・ 大網・田麦俣・志津・本道寺・白岩などの各宿には常に伝馬と人足の備えがあり、時には人をおんぶして運ぶ事もあったという。 ところで、江戸時代庄内藩主の参勤通路は清川から船で最上川を上り、舟形から羽州街道に出、更に奥羽街道を江戸に上るというきまり。しかし、天保五年(1843)は大雪で翌六年の春になっても残雪が多く、清川口が危険であったため六十里越街道を通って江戸へ参勤している。また、秋田藩主もこの道を通って江戸へのぼった記録が残されている。江戸時代の六十里越街道はまさに全盛を究めた時代でもあった。