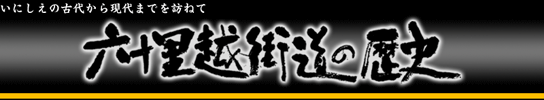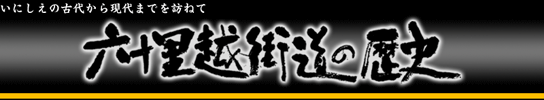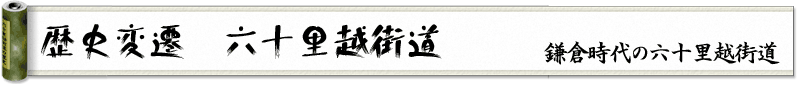 |
 源頼朝が平氏を滅ぼし、建久三年(1192)征夷大将軍に任命され鎌倉に幕府を開く。その頃、出羽国を含め奥羽他方は藤原三代の支配下にあって平和が保たれていた。平氏滅亡に戦功のあった源義経は兄頼朝と不和になり、やがて義経は追われる身となって畿内各地を転々と
した後、幼年かくまってもらった藤原秀衝をたよって奥羽に下った。「義経記」にはその道中、山伏に変装した一
行はある時は羽黒山伏、またある時は熊野山伏と称して世を忍び北陸道を通って越後路より鼠ケ関に入り、
田川・大梵字・清川を通って平泉に行った、と記している。ここには出羽三山信仰の道が登場する。また、山形
市鈴川の一明院裏手の糖塚の板碑には「月山行人結集等、己土百人敬白、貞治七季年戊申三月日」と刻まれている。
鎌倉時代に山形付近の者が百人の講を組んで月山に参詣している事を物語る記録が今日に残っている。平安から鎌倉時代にかけての出羽三山の信仰の中心は月山にあった事が伺える。
源頼朝が平氏を滅ぼし、建久三年(1192)征夷大将軍に任命され鎌倉に幕府を開く。その頃、出羽国を含め奥羽他方は藤原三代の支配下にあって平和が保たれていた。平氏滅亡に戦功のあった源義経は兄頼朝と不和になり、やがて義経は追われる身となって畿内各地を転々と
した後、幼年かくまってもらった藤原秀衝をたよって奥羽に下った。「義経記」にはその道中、山伏に変装した一
行はある時は羽黒山伏、またある時は熊野山伏と称して世を忍び北陸道を通って越後路より鼠ケ関に入り、
田川・大梵字・清川を通って平泉に行った、と記している。ここには出羽三山信仰の道が登場する。また、山形
市鈴川の一明院裏手の糖塚の板碑には「月山行人結集等、己土百人敬白、貞治七季年戊申三月日」と刻まれている。
鎌倉時代に山形付近の者が百人の講を組んで月山に参詣している事を物語る記録が今日に残っている。平安から鎌倉時代にかけての出羽三山の信仰の中心は月山にあった事が伺える。
出羽三山の三山登山がいつから始まったかについても明らかな記録はない。一般民衆が行者となって参詣しだしたのは平安ごろから比較的平和が保たれた鎌倉時代にかけて。以後室町時代は羽黒派山伏の活躍が著しくなり、出羽三山の中でも湯殿山へと信仰の中心が移っていく。当然のことながら湯殿山参詣へ上る道六十里越街道は中世後半に至って信仰の道の檜舞台として脚光を沿びていくのである。
|
|