全調査地に共通して分布する樹種はオノエヤナギのみですが、タチヤナギ、タニウツギ、ヒメヤシャブシ、サワグルミなども中洲を構成する代表的な樹種でした。調査地全体ではヤナギ類6種(オノエヤナギ・タチヤナギ・イヌコリヤナギ・ネコヤナギ・シロヤナギ・オオバヤナギ)、先駆樹種5種(タニウツギ・ヒメヤシャブシ・タニガワハンノキ・ミヤマカワラハンノキ・サワグルミ)、二次林構成樹種11種(オニグルミ・ミズナラ・イタヤカエデ・トチノキ・オオヤマザクラ・ヤマグワ・ヤマモミジ・オオバクロモジなど)の合計22種が生育していました。
全調査対象樹種の本数は823本であり、そのうちヤナギ類が65%(533本)を占め、先駆樹種が26%(212本)、二次林構成樹種としたものはわずか9%(78本)でした。これより、中洲を構成する樹種は侵入が早く、流水による影響にも比較的強い樹種が多いことがわかった。
次に、調査地ごとにみると、中洲Aではタチヤナギがもっとも多く、オノエヤナギ、ネコヤナギ、イヌコリヤナギなどのヤナギ類、タニウツギ、ヒメヤシャブシなどの先駆樹種が多くを占めるが、ミズナラなども生育しています。中洲Bではオノエヤナギとタチヤナギが圧倒的に多く、わずかにタニウツギなどの先駆樹種が生育するのみとなっています。中洲Cはオノエヤナギの占める割合が圧倒的に多く、ヤナギ類以外の木本類の生育はいっさいみられなかった。中洲Dではオノエヤナギ、タニウツギ、サワグルミなどが多いが、イタヤカエデやオオヤマザクラといった2次林構成樹種も多く生育しています。中洲Eはオノエヤナギが多く、イヌコリヤナギなどのヤナギ類、タニウツギなどの先駆樹種で構成されています。もっとも種類数が多い中洲Fではオノエヤナギ、タニウツギなどが多いが、オオバヤナギやホオノキ、ミズナラなどの二次林構成樹種も多く生育していました。また、今回の調査地のなかでは唯一、シロヤナギの生育が確認されました。中洲Gはタチヤナギ、タニウツギが多く、ミズナラ、トチノキなども生育していました。
中洲の主要な構成樹種であるヤナギ類について、オノエヤナギ、タチヤナギに共通していえることは樹高1〜2m、直径1〜2cmの個体がもっとも多く、イヌコリヤナギ、ネコヤナギについてもほぼ同じ傾向が見られました。しかし、オノエヤナギは樹高10〜15m、直径10〜15cmの高木も比較的多く分布していました。タチヤナギは樹高4m以下、直径5cm以下にそのほとんどが分布し、高木の生育は少ない。オオバヤナギは樹高5m以上、直径6cm以上に分布し、高木、もしくは亜高木となっている。シロヤナギは生育本数は少ないが、樹高20m、直径も30cmを超える高木となっている。ことなどが判りました。
|
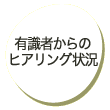
![]()