各中洲について、どの位置にどんな樹種が分布するかをみると、中洲の流路側や上・下流端部分にはヤナギ類や先駆樹種が多く分布していました。そして、流路から遠い中洲中央部分などにはオオバヤナギや二次林構成樹種の分布が多くみられるようになり、オニグルミやミズナラの幼樹は比較的流路に近いところにも分布していました。これは、これらの種子が流水にのって中洲に侵入し、定着したためと考えられます。
それぞれの中洲における構成樹種の分布の模式図を図1−(1)〜(7)に示してありますが、中洲Aは流路側にタチヤナギが多く分布し、中央部に向かっていくに従ってオノエヤナギ、オオバヤナギなどのヤナギ類、ミズナラなどが生育しています。中洲Bは一様にオノエヤナギ、タチヤナギが分布しています。中洲Cは中洲先端部などにはススキ、ツルヨシなどの草本類が生育し、オノエヤナギが全体的に分布しています。中洲Dは周縁部にわずかにオノエヤナギなどが生育するが、サワグルミやタニウツギなどの先駆樹種の生育範囲が広く、中央部では2次林構成樹種やオオバヤナギの分布がみられました。中洲Eはオノエヤナギの占める割合が高く、先駆樹種も流路側から中央部にも生育しています。中洲Fは流路側、先端部などにヤナギ類や先駆樹種が多く、中央部にはミズナラやオオバクロモジなどの2次林構成樹種やオオバヤナギなどが生育しています。また、一部にはススキの群落も成立しており、非常に複雑な構成をみせいいます。中洲Gではタチヤナギが流路側に多く生育し、割合ももっとも高くなっています。先駆樹種も多くみられますが、比高の高い中央部にはオニグルミ、オオバヤナギの高木が生育しています。
このように、流路からの距離に応じてある程度、構成樹種が変化していることがわかりました。しかし、これらの構造も中洲によって異なることが多く、平面図のみで中洲と構成樹種との関係を示すことは困難であると言えます。
|
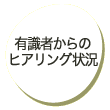
![]()