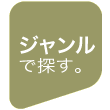|
長井市立長井小学校 4年3組(30名)
「河川から環境を考えよう」
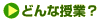
授業時間:総合的な学習の時間のうち40時間
また、国語の時間(長井市内にある橋について13時間)や社会の時間(家庭やスーパーなどからでるゴミについて25時間)とリンクさせ、知りたいことをより深めた授業が行われました。
授業の流れ:
〇授業内容の決定
「環境について調べるならどんな事がしりたいか」というテーマで話し合いが行われました。身のまわりで現在気になっていること、自分がやりたいとおもっていることなどを話し合った結果、「水」と「空気」に分かれました。徹底的に相談、最後はディベートになりながら8時間をかけ、「河川から環境を考える」ことに決定しました。
↓
〇授業の方向性を決定
『河川』の何を調べたいのかについて話し合いました。そして、自分の調べたい事を決め、同じテーマの児童同士集まり、4つのグループ(①川の水質、空気②川の周辺のごみ③地形、川幅、深さ④水生昆虫、川底の様子、砂・石・どろ・水草)に分かれました。テーマが決まった後、「何をどのように調べたいのか」「どんな資料が必要なのか」「どのくらいの時間がかかるのか」計画表を作成。「準備するものは何か」など詳しい計画を立てて、授業が進められました。
↓
〇調査
現地の見学については、それぞれがグループごとに学びたい目的を持ちながら、一緒にでかけました。
調査内容/聞き取り調査(家族・地域にすむ人・現場の人)
インターネットで検索
河川のごみの現状調査
水質調査
文献・資料・からの調査
現場見学(最上川・野川/上流・下流)
↓
〇まとめ。
・わかったことをグループで模造紙にまとめました。
↓
〇発表会
模造紙にまとめたものを、グループごとに発表しました。
〇その他
・国語では「アーチ橋の仕組み」を学習し、自分達の身近にある橋はどんな橋なのか、橋のある場所・橋の幅・長さ、外観・色、工事費、橋がつくられたきっかけなど外部講師を招いて教えてもらいまとめました。そして、生活圏にある橋を学んでいた長井小学校の6年生と、国語の授業で同じ「アーチ橋の仕組み」を学んでいる鷹山小学校の4年生に詳しく知らせるために、ビデオレターを作成し、伝えました。
|