砂が主要な構成土砂である中洲を「タイプI」とし、礫の堆積が多い中洲を「タイプII」、中洲中央部などに腐植層が発達している中洲を「タイプIII」とすると、タイプIには中洲Bと中洲E、タイプIIには中洲A・中洲C・中洲G、タイプIIIには中洲Dと中洲Fがそれぞれ該当します。
タイプ別に中洲の特徴を見ると、タイプIは砂の堆積が多く、中洲Bが33.7cm、中洲Eが43.4cmと全体的な比高は全調査地のなかでもっとも低くなっています。砂防ダム上流部など、特定の条件によって砂が堆積してできた可能性が高く、中洲の成立段階としてはもっとも初期の段階であることが考えられます。したがって、ヤナギ類や先駆樹種が構成樹種の大部分を占めています。また、個体サイズも大きくならずに、タチヤナギなどは矮性に成長する個体もみられます。特に中洲Bではそれが顕著にあらわれており、浸水、または冠水の頻度が高いことが予想されます。ここでの樹冠はおおよそオノエヤナギによって占められています。
タイプIIは礫の堆積によって中洲が成立しており、全体的な比高は高くなっています。また、川幅が狭いところにできており、中洲の全長、幅とも小さい傾向があます。このタイプの中洲はタイプIのような中洲の成立後に礫が堆積して成立した可能性と、大規模な出水によって一度に成立した可能性が考えられます。また、中洲の中央部には砂が堆積しているものが多く、一部分では腐植層も発達しています。調査対象となったヤナギ類のうち、シロヤナギを除く5種が生育し、先駆樹種や二次林構成樹種も分布している。オノエヤナギやオオバヤナギなどの高木が樹高10mを超えるようになり、上層はこれらのヤナギ類によって占められます。下層にはそれ以外のヤナギ類、先駆樹種などが占めており、2段林を形成しています。また、タチヤナギは流路側などの限られた場所に生育していますが、オノエヤナギ同様に主要な構成樹種となっています。ネコヤナギやイヌコリヤナギの生育がみられるのもタイプIIの特徴です。また、このタイプの中洲がもっとも多くみられ、構成樹種からみてももっとも一般的な中洲ということがいえます。
タイプIIIは流路側には礫の堆積が多く、中央部分では腐植層の発達が進んでいます。中洲の全体的な比高はタイプII同様高くなっており、中洲の大きさはタイプI、タイプIIと比べると大きく、中洲D、中洲Fのいずれも全長100mを超え、幅も30〜50mとなっています。成立過程として、タイプIIの成立後に腐植層が発達し成立した可能性と、従来川岸だったところが何らかの原因によって分断され、中洲となった可能性の二つが挙げられます。今回、調査を行った中洲のうち、中洲Fは後者による成立の可能性が高いと考えられます。また、中洲の流路側などではヤナギ類が優先するが、中央部ではそれ以外の構成樹種の割合が大きくなっています。特に二次林構成樹種の多くは腐植層の発達しているところに生育しています。しかし、これらの個体サイズは小さく、タイプII同様、上層を占める高木ヤナギ類とで2段林を形成しています。タイプIIでの樹冠はオノエヤナギが占めていたが、タイプIIIではオオバヤナギがそれを上回るようになっています。
|
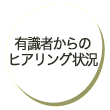
![]()