山地渓流の川岸は流水の影響を受けるため、非常に立地環境が不安定です。そのため、そこに成立する森林は周辺の山地林とは異なった多様な植物群落が複雑に分布しています。
これらの森林を構成する樹種の特徴として、長時間水をかぶったり、洪水に伴う土砂による埋没や物理的損傷に強い特徴を持っています。ヤナギ類やハンノキ類などを中心に、サワグルミやトチノキなどが代表的な樹種となっています。なかでもヤナギ類は裸地で湿った場所であれば容易に発芽、成長することが可能であり、ヤナギ類は水流沿いに多く自生します。
川のなかの中洲に自生する植物は、川によって外部から隔離されるため、動物などが種を運び込む可能性が低く、川の影響だけを受けています。中洲は一般に河川によって運搬された土砂が堆積したものですが、成立する場所や構成土砂の違いなどよって中洲もいくつかのタイプにわけられます。山地渓流域では主に礫の堆積によるものが多くみられますが、ある条件のもとでは砂などの細粒土砂の堆積によるものもあります。このタイプの違いが中洲に自生する樹種にも影響を与えていることが考えられます。本編では山地渓流域に成立する中洲を対象に、その中洲の土砂から特徴を捉え、そこに生育する樹種との間にどのような関係があるかを述べてみます。
|
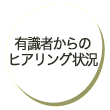
![]()