樹木の根元の水面からの高さを検討すると、比高0cm以下、つまり浸水域に生育するのはオノエヤナギとタチヤナギ、タニウツギの3種類に限られていました。比高が高くなるにつれてヤナギ類の割合は減少し、先駆樹種や二次林構成樹種が増加しています。比高0〜50cm、51〜100cmではヤナギ類が70%近くを占めているのに対し、101〜150cmでは50%程度にまで減少し、151〜200cmでは約40%、201cm以上では20%を下回るまでに減少していることがわかりました。
ヤナギ類だけをみてみると、オノエヤナギはどの比高でも分布しており、294本と生育本数ももっとも多くありました。また、タチヤナギは比高0cm以下では植生の40%程度を占めるなど、浸水域のような条件の厳しいところでの生育が可能であるが、比高が高くなるにつれてその割合は減少し、比高200cmを超える場所にはまったく生育していませんでした。
また、各調査中洲の平均比高と、中洲に生育する樹木に占めるヤナギ類の割合を検討すると、もっとも平均比高の低かった中洲B(33.7±1.74cm)のヤナギ類の割合は83%であった。一方、もっとも比高の高かった中洲D(161.7±7.86cm)ではヤナギ類の割合が20%と、もっとも低い割合となりました。
さらに、中洲の平均比高が高くなるにつれてヤナギ類の占める割合が小さくなっています。このことからもヤナギ類は比高が低い、つまり、流水による影響を受けやすいところでの生育に適しているということが言える。逆に比高の高い、つまり、安定した立地環境では新たな侵入が困難になり、それ以外の構成樹種との競争に負けてしまうことが考えられます。
代表的なタチヤナギとオノエヤナギを較べると、タチヤナギは比高にあまり影響を受けることなく成長できるものの、比高が高くなり他樹種との競争が生じるようになると、ある程度で成長量が抑制されていることが考えらます。また、さらに時間が経過すると完全に被圧されてしまう可能性も考えらます。一方、オノエヤナギはほとんどの中洲の上層部分を占めていることなどから、中洲が成立した直後に侵入し、比高が高くなり他の樹種が侵入してきても比較的安定した成長を続けることができることが考えられる。比高が低いところでも同様に成長を続けるため、中洲のような特異な環境下での生育にもっとも適している樹種であるということが考えられます。
|
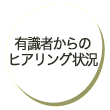
![]()