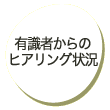“…吹雪の吹きすさぶ真冬の季節は、小国川・最上川などの大河の川面も、流れの緩やかな淵(よどみ)のところには氷(「すが」という)が張る。氷結は岸の方から始まり、次第に沖の方に延びて行く。氷の上には雪が積もる。沖の方の氷が一部割れて流れ出す。小国川の「すががえ」は、こうした季節の晴れ間をみて行う漁法で、岸から半径一〇メートル前後の沖の箇所(比較的浅いところを選ぶ)の氷雪を固く踏んで川底まで沈め、堤防のようにして内部の魚が逃げられないようにする。これを次第に岸の方に拡大し、魚の隠れる範囲を狭める。最後にその内側の氷や雪を踏み込んで、スコップやカエスキ(雪べら)で掻き回し、雪の間にささり込んだ魚を雪と一緒に掻き上げる。魚は雪の上でピチピチ跳ねるが、これを拾うようにして獲る。ハヤ・フナ・コイ・ナマズなどが主な漁獲であった。
「すががえ」は、順序よく、素早く事を運ばないと、折角、踏みしめた氷雪の堤防もすぐに押し流されてしまうから、通常仲間数人組みになって行う。漁後は、この仲間一同で盃を交わし、獲った魚を味わう。仲間の楽しみの漁でもあった。…”
(「 5 雪の漁法」 p182 より抜粋)