| あるときヘンな外国人に
「なぜ母なる最上川で、父なる川ではないのですか。川は女性名詞なのですか」
と、聞かれた。答えにつまり、とっさに
「それは子供たちに最上川が子守唄をうたってくれたからです」
などと、言ってしまったがまんざら嘘ではない。川遊びをして大きくなった子は夜眠る前にあすどんなところへ行くか、川の流れや楽しい瀬音に、あれやこれやと思いを馳せる。
本川はともかく、小さな支川はたくさんの子供たちを引きつけ、育ててきた。
かの岸に何をもとむるよひ闇の最上川のうへのひとつ蛍は
と、うたった齋藤茂吉の心境は子供たちにもあてはまった。全長232キロ、県土の70%を占める最上川は県民歌にもなっている。
広き野をながれゆけども最上川 うみに入るまでにごらざりけり
昭和天皇の歌である。戦後に作者である天皇が山形県内を幸行されたとき、疎開していた歌人の齋藤茂吉に会いたいと申し出があった。茂吉は門人のいる大石田に仮住いしており、それを聞くとかたく辞退した。理由は
「お小水が近いので粗々があるといけない」
天皇陛下の目の前でお手洗いに立つのは気がひける、ご容赦願いたいというていねいな返事を宮内庁へだした。すると陛下は
「そのようなことはかまわない。ぜひ歌の話をしたい」
と、再度にわたる誘いがきた。陛下は自作について、茂吉の評を聞きたかったらしい。
謁見は茂吉のふるさと上山市の旅館で行われ、ご下問は
「この歌はどうであろう」
と、核心を突かれた。茂吉はしどろもどろ
「最上川は大河でございます。海に入るまでにごらないわけにはまいりません」
四三四の支川をひとつに引き受ける川の雄大さと雪解け水の多量さをそれとなくご説明申し上げ、話がはずみ、予定より時間が長びいてしまった。茂吉は緊張のあまり
「尿意を忘れた」
と、門弟たちにもらした。仮住いの世話をした板垣家子夫さんはみずからも
わが産湯に最上川水汲ましめし父逝きて遠しかかる世も遠し
中流部の大石田出身らしい歌をつくっており、茂吉と最上川の話をさせると、もうとどまるところがなかった。最上川という歌題でとことん川とつきあい、一河川をテーマにとり組み、歌集を編んだ例を、私は他に知らない。師と弟子は二人三脚で作歌にはげみ、
「私の仕事は最上川をうたうことです」
こう言うまで入れあげた。ひとくちに最上川といっても舟運時代の川とは様変わりして物を運んだり、受けとったりする川湊の役割は消えてしまった。景観や県土をはぐくんできた最上川を、茂吉は生れ育った自分の原風景としてとらえようとしたのか。私は中流から舟下りをする船上で、歌人の視点を考えた。
はたして何が彼をそんなふうに魅了したのか、答えを探したかったのである。
三難所である碁点、隼(はやぶさ)、三ヶ瀬をすぎると急に川幅がひろくなり、心持ちゆったりした流れになるが、川底は急峻できびしく、川面とはだいぶ違うらしい。朴訥で無口な山形県人のように見えるが、秘めたエネルギーはうず巻く川床にあるようだ。船頭泣かせもこのあたりにコツがいったのだろう。
全国的に舟運の歴史はめずらしくないのに、船頭はまことに少ない。
ボルガの舟唄のように、川と切っても切れないセットになっている川の名をほとんど聞かない。最上川舟歌も、もともと船乗りたちが歌っていた本歌が消えかかっているのを編詞、編曲して現代風に生きかえらせた。櫂の漕ぎかたや竿のさしかたに力がこもり、かけ声がついて、人と舟の呼吸がじつにみごとだ。
「櫂は三年、櫓は三ヶ月」
と、いわれるぐらい櫂の使い方はむつかしく、うまい船頭に当たると舟は座敷にいるような安定感があり、しかも単調でギィー、ギィー、と眠くなるような音になってしまう。
酒田さ 行ぐさげ、達者でろちゃ
流行風邪など ひがねよに
碁点 隼 やれ三ヶ瀬も
達者でくだったと 頼むぞえ
山背風だよ あきらめしゃんせ
おれをうらむな 風うらめ
舟下りにとって風は大敵で、風に流されると櫂の調子が狂い、ぐいぐいと引っぱられる。天候との勝負であった。そうした四季の最上川を身近な生活者の目で茂吉は歌にした。
最上川のほとりをかゆきかくゆきて小さき幸をわれはいだかむ
この水で産湯を使った安らぎは知らず、知らずのうち歩いてきた年月になった。若いころは心せかされ、静かに川を見る余裕などなかったが、こうして川のほとりを何気なく歩いているだけで、小さな幸せを感じるゆとりができてきた。おそらく大石田に住んだときから茂吉は芭蕉を意識していたにちがいない。
あるがままの自然をどう受けとめてゆくか。
自然に没入した芭蕉を羨ましがったのかもしれない。芭蕉が詠んだ
五月雨を集めて早し最上川
スピード感と時間の音を感じさせる句に対抗し、茂吉は五月雨どきにしばしば現われる紅に目をむけた。雨あがりの空へまるで最上川への天の橋をかけるような色彩が、線を描く。
それはどんな人生にも思いもかけない華やぎや色どりがあるのを、知らせる天の恵みである。奇跡のように現われて、消えてゆく。
最上川の上空にして残れるはいまだうつくしき虹の断片 (大石田町民歌)
もはや来し方、ゆく末を考える年齢になり、我が身につくってきたいくつかの流れも見えてきた。しかも思い出はいつも美しく、だがそれさえ断片になり、定かではなくなってきた。しかし心の流れにかかった虹は今もはっきりと思いだすことができる。
茂吉の感慨は最上川に時の音を聴いたものであろう。それは永遠の子守唄なのである。
|
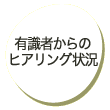
![]()