成長錘を使用して各中洲に生育するオノエヤナギの樹齢を調べたところ、中洲D、中洲Fでは樹齢40年を超えていることが推定され、中洲A、中洲C、中洲E、中洲Gでは樹齢20〜25年と推定されました。なお、中洲Bでの成長錘を使用した樹齢の調査はできませんでした。加えて、航空写真を用いて中洲の成立の有無を判定した結果、中洲の成立順をD・F→G→A・E→C→Bと推定しました。これより、タイプIIIに該当する中洲Dと中洲Fがもっとも古く、タイプIに該当した中洲Bがもっとも新しい中洲であることも確認されました。
これまでの調査結果より、中洲の成立過程を推定したものが図2−(1)、図2−(2)、図2−(3)である。調査した中洲の成立過程には以下の3つのパターンが考えられます。
砂防ダム上流部などに土砂が堆積して中洲が成立するのがパターン(1)です。初期段階ではオノエヤナギやタチヤナギなどのヤナギ類が入ってきます。その後の出水などで砂の侵食、礫の堆積などが起こり、徐々に中洲の比高が高くなっていくに従って先駆樹種であるタニウツギ、ヒメヤシャブシなどが生育し始めます。また、さらなる時間の経過とともに腐植層が形成され、オニグルミなどの2次林構成樹種が生育するようになることが考えられます。しかし、このような砂の堆積は砂防ダム上流などの限られた条件のもとでしか起こらないため、山地渓流域においては一般的な中洲の成立過程とは考えにくいものです。
次に、洪水などの大規模な出水で大型の礫などが一ヶ所に堆積して中洲が成立するものがパターン(2)として考えられます。最初から中洲の比高がかなり高くなっているため、ヤナギ類はもちろんのこと、先駆樹種の侵入もある程度容易になっていることが考えられます。また、流路から離れれば離れるほど流水による影響を受けにくいため、腐植層が形成されやすく、2次林構成樹種の生育が可能となります。山地渓流域ではこのような礫の堆積が比較的高い頻度で起こることから、もっとも一般的な中洲の成立過程と考えられます。
パターン(3)は大規模な出水、あるいは人為的な行為によって、もともと川岸だったようなところが分断され、中洲の状態となったものです。よって、初期段階には周辺の河畔林同様の植生がみられると考えられます。しかし、中洲の流路側は河川の営力によって浸食され、礫などが堆積していくため、オノエヤナギなどのヤナギ類が侵入し、生育し始めます。
このように、中洲の構成土砂、つまり、特徴は時間の経過によって変化していっているということがわかる。
|
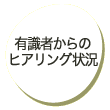
![]()