|
1.舟運機構の成立
・最上義光の三難所開削、三河岸の設置
最上川三難所とは、村山市の碁点、三ヶ瀬、隼(早房)のことである。この3ヶ所が最上川は大きく蛇行し、流れも急になるところで、松尾芭蕉も『おくの細道』に「碁点、隼、三ヶ瀬というおそろしき難所あり」と記している。この難所を最上義光が開削し、舟運が発展するきっかけとなった。また、中流部には舟運の基地となった新庄盆地の清水、山形盆地の大石田と船町の三河岸がある。慶長年間に大掛かりな整備が行われ、江戸時代を通じて経済の発展に貢献した。
・大石田船、酒田船の片運送
大石田は最上川の中流部にあり、山形盆地の入口でもあったことから、舟運において重要な位置を占めていた。ここで荷物を積む船が多く、河口に位置する酒田と並んで繁栄を極めた。慶安年間には上り荷は酒田船、下り荷は大石田船に限るという「片運送」が始まった。この片運送は幕末まで行われた。
2.西廻航路の整備と最上川舟運
・西廻航路の整備と酒田(寛文12、1672)
江戸の経済が発展し、人口が多くなるにつれて、江戸での米不足が深刻な問題となった。そこで、最上川流域の幕府領で収穫された年貢米を江戸に運ぶための西廻航路の整備のために、幕府の御用商人の河村瑞賢が派遣された。瑞賢は寛文12(1672)年に酒田を起点とした西廻航路を確立し、これによって酒田は「西の堺、東の酒田」と称され、隆盛を極めた。
・元禄時代の発展(川船、輸送物資)
元禄時代には河岸と船着場が発達した。代表的なものとして、酒田、清水(大蔵村)、大石田、左沢(大江町)、宮(長井市)などがあるが、特に栄えたのは酒田と大石田である。松尾芭蕉が山形県を訪れた頃は、大石田が最も栄えていた時期である。輸送物資は、当初の目的が年貢米の廻送だったことから米が主であったが、やがて紅花や青苧、大豆などの特産品も京都方面に移出されるようになった。移入品としては塩や茶などが挙げられる。
・最上川上流(松川)の舟運開発
元禄7年、米沢藩の西村久左衛門が、米沢から左沢までの舟路を開いた。酒田が西廻航路の起点として繁栄した一方で、米沢では米の輸送に苦労していた。米沢藩の西村久左衛門は船の通行ができない松川の黒滝を開削すれば藩に利益がもたらされると提案したが、財政難を理由に、藩としての開削は行われなかった。そこで久左衛門は独力で整備を行い、輸送物資の量も飛躍的に伸び、置賜から村山への舟運が発展することになった。
3.江戸中期の川船差配役制
・川船差配の刷新(享保8年、1723)
元禄時代に栄えた大石田では、最上川の舟運を独占的に支配する商人がいた。元禄年間の末頃になると、利害関係も絡み、この独占支配に反発する商人が現れた。この動きは年々強まり、享保8(1723)年に大石田川船差配役が廃止され、5人の商人・百姓代表によって川船が差配されることになった。また、片運送の廃止と入会運送の実施、寺津・本楯・横山を新たに河岸として認可することなどが決定された。
・差配役制の展開と混乱
享保8年に大石田川船差配が廃止されてから、舟運は5人の商人・百姓代表によって差配されてきた。大石田の川船差配はその独占性を嫌われて排除されていたが、延享4(1747)年からは再び大石田の差配役が参加するようになった。宝暦10(1760)年に差配役が請負・入札制になると大石田出身の差配役はさらに増え、交替も激しくなった。享保年間以後は川船の数は減少し、その統制も混乱した。
4.川船役所の設置と川船惣代制
・寛政4(1792)年の川船役所の設置
宝暦年間以後、次第に混乱してきた川船差配役は行き詰まり、寛政4(1792)年に従来の請負差配役が廃止され、幕府の直差配となった。大石田川船役所が設置され、尾花沢代官所の管轄となった。川船役所には船会所が付属され、船方惣代をおいて運送の統制にあたった。統制を強化したことで最上船が増加するなどの効果もあったが、初代惣代の死亡をきっかけに、再び混乱の時代を迎えることとなった。
・大名手船の増加(新庄藩、米沢藩、佐倉藩)
最上川の川船は町船中心であったが、江戸中期以降、大名手船が少しずつ増加した。米沢藩、新庄藩、佐倉藩分領で見られたが、これは認可に制限があった。幕末には寺津と船町との間で河岸間紛争が起こった。船町が佐倉藩の河岸として特別保護のもとに発展し、それまで最大の河岸であった寺津に打撃を与えたのが原因である。天保13(1842)年にこの紛争は解決したが、その後もたびたび問題を繰り返した。
・最上川船株の設置
ひらた船の経営は近世後期になるにつれて苦しくなり、それが原因となってひらた船も減少していった。これを食い止めるため、天保3年に最上川ひらた船株が設けられた。ひらた船の保護とともに、江戸への年貢米の確保も目的の一つであった。船株は大石田に集中しているのが特徴で、無株の船は荷物の取扱いを禁じられた。
・小鵜飼船の台頭
西村久左衛門が元禄7(1694)年に開削した松川は、蛇行が多く流れが急なため、ひらた船は通れなかった。そのため、米沢藩は宝暦9(1759)年に阿武隈川に派遣されていた今成平兵衛を起用し、最上川に合った小鵜飼船を作らせた。以後、松川では小鵜飼船がよく見られるようになった。前が細く、中央部にかけてふくらみ、後ろが狭い独特の形により、舵取りがしやすく速度も出るのが特徴である。化政年間には数が増え、禁止されていた本流へ進出したことが問題となった。
・江戸期の舟運制廃止(明治5年、1872)
本流での小鵜飼船の運航は禁止されていたが、実際は本流での就航も多く、明治3(1870)年には小鵜飼船差押一件という事件も起こっている。明治5(1872)年に江戸時代の制度が廃止され、本流での通航が自由化された。
5.明治期の最上川舟運(小鵜飼船、乗船常便社、酒田回漕会社)
明治5(1872)年に小鵜飼船の本流輸送が解禁されたことで、江戸時代には禁止されていた左沢より下流でも、小鵜飼船が多く利用されるようになった。明治12(1879)年には荷物輸送を主とした酒田回漕会社が設立され、続く14(1881)年には旅客輸送を目的とした乗船常便社が設立された。県でも蒸気船を運航する計画があったが、財政難のために実現しなかった。20年代には上り船での貨物輸送が計画された。詰まれた荷物は上りは雑貨・海産物など、上りは米・石炭などが多く、上りの物資のほうが多かった。30年代は年を追うごとに輸送は減少の傾向を見せはじめ、36(1903)年に奥羽本線が開通したのに伴って、交通基盤としての機能を失った。

|
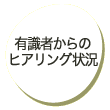
![]()