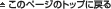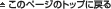あ行
- アンモニアイオン
- アンモニウム態窒素は主として尿や家庭下水の有機物の分解と工場排水に起因するもので、それらによる水質汚染の有力な指標となります。また富栄養化の原因ともなります。このアンモニウム態窒素は水中では大部分アンモニアイオンとして存在します。
- 雨量強度
- 降水量の強さを表しています。一般に、時間雨量何mmというのは、1時間に降った雨の量です。強い雨でも、10分間ではさほど大きな値にはなりません。雨の強さを比較できるように、ある時間内の強さの雨が1時間続いたとした場合の雨量を雨量強度として表現します。
- 一級河川本川
- 一級河川は国土保全上または国民経済上特に重要な一級水系において、国土交通大臣が国土交通省令により、水系ごとに名称・区間を指定しています。同じ水系の中で流域、長さ、流量などが最も大きい河川を本川と呼びます。
- SS(濁度)
- 水中を濁している水に溶けない粒状の物質の量をいいます。この粒状の物質は、粘土や動植物の死ガイ、下水、工場排水などの有機物や金属のゴミなどです。量が増えると水が濁り、透明でなくなり、見た目が悪くなります。
- 塩素イオン
- 塩素イオンは海水中に約19000mg/L、河川水中には一般的には数mg/L含まれています。海岸地帯では海水の浸透、風による巻き上げ等の影響で河川水中の濃度が高くなることがあります。それ以外で塩素イオンが増加した場合、家庭排水、工場排水、し尿等の混入汚染が考えられ、人為的汚染の有無を判断する材料となります。
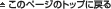
か行
- かんがい用水
- 田畑を潤すために人工的に水田や畑に引かれる水のことです。農作物の生育に必要な水で、農作物の増産や景観の維持、乾燥地帯や乾期の土壌で緑化する目的で使用されます。
- 危険水位
- 「洪水予報対象河川」の主要な水位観測所に設定される「氾濫の恐れが生じる水位」で、洪水予警報の発表において用いられます。
- 空立米
- 普通の㎥(立方メートル)と㎡(平方メートル)については、それぞれ体積と面積の単位ですが、空㎥は主に支保工の積算で使われる単位で、空の内部空間も含んだ体積になります。
- 警戒水位
- 水防法の「水防警報対象河川」の主要な水位観測所に定められている水位です。同法で定める各水防管理団体が、水害の発生に備えて出動し、又は出動の準備に入る水位です。
- 計画高水位
- 堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組みあわせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。河川の計画上の水位なので、堤防が完成していなければ、この水位より低い水位で氾濫などが発生する可能性があります。
- 検定済みデータ
- 観測値をチェック・確認等により検定し、公的に真値として発表されるデータです。個別チェックや統計的処理を行い、誤っていると考えられるデータを修正・削除したデータです。現在、検定は、データをまとめて実施されるので、数ヶ月以上の日数を要します。検定済みデータについては、トップ画面の「検定済みデータ」(水文・水質データベース)で閲覧できます。
- 洪水警戒体制
- 山形地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が出されたときにとる体制。
- 洪水予報
- 大雨などにより災害が発生する恐れがある場合に出されるものです。気象庁が発表する洪水予報と国土交通省と気象庁が共同で発表する洪水予報があります。国土交通省は2以上の都道府県にわたる河川または流域面積の大きい河川で大きな損害が生ずるおそれがあるとして指定した河川について、洪水のおそれがあると見とめられるときはその状況を気象庁と共同で発表して関係都道府県に通知し、合わせて一般の方々にもお知らせします。洪水予報が出される。河川は、現在、全国で192河川あります。
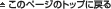
さ行
- COD(化学的酸素要求量)
- CODは水中の有機物などが酸化剤で酸化される時に消費される酸化剤の量を酸素の量に換算したもので、有機汚濁の指標としてよく用いられます。CODの測定法にはいくつかありますが、わが国では過マンガン酸カリウムを酸化剤に用いて、試料を酸性で反応させて測定する方法(100℃で30分間反応させたときの過マンガン酸カリウムの消費量から換算する方法)が多く用いられています。
- 支川
- 本川に合流している河川を支川と呼びます。
- 指定水位
- 水防法の「水防警報対象河川」の主要な水位観測所に定められている水位です。同法で定める各水防管理団体が、水防活動に入る準備を行うための水位のことです。
- 浸透流
- 川の水位が高くなると川側から堤防内に向かって浸透流という水の流れが発生します。
洪水が長時間にわたって続いた場合、この浸透流により堤防の土砂が泥状となって流れ出し、堤防の決壊につながる恐れがあります。
- 水防警報
- 水防警報は、国土交通省または都道府県から水防管理団体の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与えることを目的して発令されるもので関係機関に通知されます。水防警報は、河川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位に対して、指定水位、警戒水位、危険水位など水防活動の目安となる水位を決めておき、川の水かさが、その水位あるいは水位近くまで上昇すると発令されます。このような水防警報が出される河川(国土交通省大臣指定)は、全国で318河川あります。
- 積雪深
- 地上に積もっている地表からの雪の厚さのことです。なお、1時間に降った雪の深さや大雪で降った1降雪の雪の深さは、降雪深といいます。
- 全国レーダ雨量
- レーダによる雨量観測の最新値を表示します。全国の各レーダでとらえた降雨状況を合成された画面として見ることができます。1マス(メッシュ)のサイズは、1辺が20kmで、その範囲の平均雨量強度を表示します。
- 速報値
- リアルタイム値とほぼ同じ意味です。提供する情報は、速報性に重点を置いているため、データの検定が行われる前の値で、観測機器や演算機器の不具合などにより、誤ったデータが含まれることもあります。
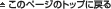
た行
- 濁度
- 水の濁りの程度を表すものです。粘土鉱物であるカオリンが1mg/Lが含まれた水を1度としています。濁りの原因となっている物質には粘土性物質、プランクトン、有機物質等があり、濁りとなる粒子の粒径は0.1から数百μm(ミクロンメートル)のものが殆どです。
- ダム放流通知
- ダムから放流する時にダム下流の関係機関にその旨を通知するものです。ダムによって貯められた流水を放流することにより川の流れに大きな変化が発生する場合にはダムの管理者は放流の日時、放流によって上昇する水位の見込みを関係知事、関係市長村長、関係警察署長に通知すると共に一般に周知させなければなりません。これをダム放流通知と呼びます。
- ダム水路式
- ダムと水路を組み合わせて水車を回転させ、発電する水力発電の方式です。ダムで貯めた水を水路で下流に導き、大きな落差を利用して発電します。
- DO(溶存酸素量)
- 水中に溶け込んでいる酸素量のことです。数値が小さいほど、水質汚濁が著しい。酸素の溶解度は水温,塩分,気圧等に影響され、水温が高くなると小さくなり、又きれいな水ほど飽和に近い量が含まれます。DOは河川と海域の自浄作用, 水生生物の生活に不可欠なものです。一般に魚介類が生息するためには3.0mg/L以上が必要であり、環境保全上からは嫌気性醗酵分解を防止し、臭気を生じない限界として2mg/L以上が適当です。
- テレメータ
- 雨量・水位等の観測所で自動観測したデータは、無線で事務所などに自動的に送信されます。このように自動的に観測・送信するシステムを「テレメータシステム」といっています。
- テレメータ水位(雨量、水質状況)図
- テレメータで、自動観測される雨量、水位等の観測所の位置を地図上に記載した図です。雨量、水位、水質等の観測所は、データの状況(上昇、下降等)でマークの形状や色が変化します。
- 導電率
- 電気伝導度とも言い、電気の流れやすさの指標です。水中に含まれる陽イオン, 陰イオンの合計量の目安になります。
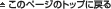
な行
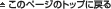
は行
- BOD(生物化学的酸素要求量)
- 生物化学的酸素要求量(水中の有機物の代表的な汚染指標【生活環境項目】)
生物が水中にある有機物を分解するのに必要とする酸素の量(mg/l)を表しています。
河川の汚染度が進むほど、この値は高くなります。
- フラッシュ放流
- 川を流れる水の量の変化が少ない状態が長い時間続くと「よどみ」が発生し、河床(川底)に藻類の繁殖や汚れなどがついたままとなったりします。 これは、環境·景観に対して好ましくありません。 ダムで貯めている水を定期的に放流することによって、 “よどみ” の発生を抑え河川をリフレッシュする効果があります。
- フランシス水車
- フランシス水車は、水力発電所で広く使用されている水車です。円周方向の外側から水を流入させ、内側に流したときの反動で回転して発電します。
- PH(水素イオン濃度)
- PHは水の酸性、アルカリ性の度合いを示す指標です。水素イオン濃度の逆数の常用対数となります。PH7が中性でそれより大きいとアルカリ性、小さいときは酸性となります。河川水は通常PH7程度ですが海水の混入、温泉水の混入、流域の地質、人為的汚染、植物プランクトンの光合成等により酸性、アルカリ性になることがあります。
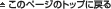
ま行
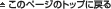
や行
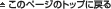
ら行
- リアルタイム雨量、水位
- 自動的に収集される最新の雨量や水位データのことです。できるだけ速くデータを提供するために、自動観測された雨量や河川水位のデータは、自動的に収集・演算して提供します。従って、ほぼ現時点のデータという意味で、リアルタイム雨量・水位といっています。なお、現在、観測所機器の整備状況によってデータの更新時間が異なっており、通常10分間隔で更新されます。
- 流域平均時間雨量
- 流域内の雨量観測所の1時間雨量をそれぞれの支配面積で重みづけし、それらの和を全流域面積で除した値です。
- 流域平均累加雨量
- 流域平均時間雨量を累加した値です。
- レーダ雨量
- レーダ雨量は、電波を水平方向に全方位360°発射し、上空の観測範囲内に存在する雨滴、氷晶、雲等から反射される電波強度から雨量を算出したものです。全国レーダ画面では、レーダ雨量として算出した上空の雨量を提供しております。「地方拡大1」、「地方拡大2」及び「地方拡大3」の各画面では、地上の雨量観測所のデータを用いて補正したレーダ雨量値を提供しています。レーダ雨量値は、その雨の強さ(10分間の平均値)が1時間続いた場合の雨量(時間雨量)として表示しています。
- レーダ雨量(履歴)
- レーダによる雨量観測の結果を過去のレーダ雨量画面として表示します。60分及び30分間隔で、過去から現在までのレーダ雨量を4時点分(例えば1時間前、2時間前、3時間前、4時間前の4時点分)で表示します。雨域の移動の様子などを見ることができます。
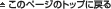
わ行