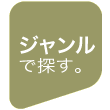| 水辺は、安らぎと潤いを与えてくれる場であり、私たちの暮らしに最も身近な自然です。だれもが川に親しみ、川で遊び、川に学ぶことができるような水辺の環境をつくろうと、県内各地で、様々な河川環境事業が進められています。 |
●桜づつみモデル事業

|
良好な水辺の空間として、古くから地域に親しまれてきた桜づつみの復活など、堤防への桜などの植樹は、多くの人々に求められています。そのため、周辺の自然、社会、歴史的な環境との関連から、必要と認定された区間を「桜づつみモデル事業」として、堤防を拡幅し強化するとともに、堤防の一部に桜などを植樹して、良好な水辺の空間を創設します。 |
| 最上川沿いでも、雄大な桜回廊をつくる整備が進んでいます。桜の植樹・管理は、各市町村で設立した組織(企業、団体、住民から募集)が主導となり、堤防の強化等を河川管理者の国土交通省や県で担当し、協力して行われています。(最上川さくら回廊整備事業については、この事業の一環として整備するものです。) |
●ふるさとの川整備事業
| 社会に潤いを与える水辺空間は、町の景観や、余暇の有効利用などの面でも大切な役割を果たしています。特に最近では、まちづくりと一体になった水辺の整備が社会的に求められています。この事業は、川本来の自然環境や周辺の景観との調和を図りながら、地域整備と一体となった河川改修により、より魅力的な水辺の空間を創設するものです。
|
●地域交流拠点「水辺プラザ」
| 川を中心とした歴史、文化や豊かな自然などをもととし、流域の人々の交流ネットワークを築き、その交流拠点や地域づくりの核となる、親水、自然の学習、休憩、交流・連携、地域のシンボル、流域・地域の情報発信など、マルチ機能のある「水辺プラザ」を整備し、魅力と活力のある地域づくりに役立てます。
|
●水辺の楽校プロジェクト
 現代の子供たちは、自然とのふれあいを通した遊び、生活体験などの機会が減少しています。河川などのもつ様々な機能を活かし、川が身近な遊び場、教育の場となるように、水辺の整備をすすめます。また、各地の教育委員会やPTAなどと連携を図りながら、「水辺の楽校」として活用されるための体制を整備します。 現代の子供たちは、自然とのふれあいを通した遊び、生活体験などの機会が減少しています。河川などのもつ様々な機能を活かし、川が身近な遊び場、教育の場となるように、水辺の整備をすすめます。また、各地の教育委員会やPTAなどと連携を図りながら、「水辺の楽校」として活用されるための体制を整備します。
これらの水辺の整備及び体制の確立により、水辺を教育の場として地域に提供します。
|
●やすらぎの川整備事業
| 平成13年度より山形県単独事業として始まった事業で、地域の人々に親しまれている河川で、すべての人に水とやさしくふれあえる川を目的に、スロープの設置や周辺環境にふさわしい親水空間の整備にあわせて、生態系にも配慮した川づくりをしていきます。 |
|