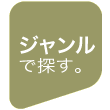江戸時代、千石船で貨幣、帳面、船往来手形、印鑑などの貴重品を入れて積み込んだのが船箪笥です。最上川河口の酒田は米や紅花を運ぶ北前船の重要な港でした。三十六人衆なる廻船問屋の豪商が繁栄し倉庫も多く、酒田は佐渡、越前と並ぶ船箪笥の三大産地でした。酒田市の七代目漆職人、伊藤久内さんは船箪笥の再興に努めています。船箪笥作りは、箪笥を組み立てる指物師と、金具や錠前を作る錠前鍛冶職人、そして漆職人との合作で、完成まで2〜3ヶ月かかります。外側は漆を何層も重ねた欅材と重厚な鉄の金具で、破損を防ぐ堅牢な作り。内部は水の浸入を防ぐ桐材で水に浮き、隠し箱が組み込まれ、かぎ代わりになる精巧な細工で盗難を防ぎます。
|
 |
|
 |
御手舟の舟タンス
(大蔵村稲沢の成沢家所蔵)
写真提供:熊谷勝保 |
|
船箪笥(懸硯[かけすずり])
(山形県立博物館所蔵) |
●関連事項/ |