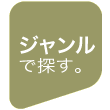| 今では日本でも有数の米どころとなっている庄内平野も、かつては大部分が不毛の土地で荒地が広がっているだけでした。この荒地を開墾しようと幾度となく川から水を引こうとしましたが、川が土地よりも2〜5mも低いため、なかなかうまくいかず、日照りの害に苦しんでいました。その頃、狩川城主になったのが北楯大学利長でした。北楯大学はなんとか水を引く方法はないものかと、10年の歳月をかけて最上川よりも高いところを流れる立谷沢川から水を引く設計図をつくりました。このとき完成した北楯大堰は、いまでも庄内平野を潤しており、庄内平野が米どころとなったのは、北楯大学が切り開いた北楯大堰のおかげと言えるほどに、その活躍は大きいものなのです。 |
 |
北楯大学利長〔きただてだいがく・としなが〕(1547〜1625)
最上義光の家臣。義光が庄内を支配した後、狩川城主に任ぜられる。土地の不毛さを知り、灌漑のための調査を始める。調査には10年の歳月をかけ、義光に開削願いを提出する。工事には4ヶ月が費やされ、ついに荒野は大穀倉地帯としてよみがえった。今でも狩川城跡の利長像が利長自身が心血を注いでつくりあげた水路とその支流、その恵みを受けた美しい水田を見つめている。 |
|

現在の北楯大堰(きただておおぜき)
●関連事項/ |