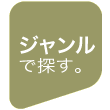今のように鉄道や自動車など、陸の交通機関が発達していなかったころ、荷物を運ぶ手段は船でした。最上川は、江戸時代に山形城主最上義光らにより上流から河口まで航路が開かれると、たちまち主要な輸送路となり、舟運が発達していきます。山形の物資は酒田から下関を通り、上方(今の大阪や京都)、江戸へと至る「西廻り航路」で運ばれました。行きの船には米・大豆・紅花・青芋・煙草などが送られ、帰りの船には、塩・魚・茶・古手(古着)・雛人形・仏像・石灯篭などが積まれてきました。山形は江戸や上方とつながることによって、経済だけではなく文化にも大きな影響を受けました。河北町の紅花資料館や酒田市の本間家旧本邸などで知られる雛人形はその代表ともいえます。経済や文化の交流の舞台となった最上川ですが、1903年(明治36年)に奥羽本線が新庄まで開通し、1914年(大正3年)に陸羽西線が開通すると、その役割は鉄道へと移り変わっていきました。
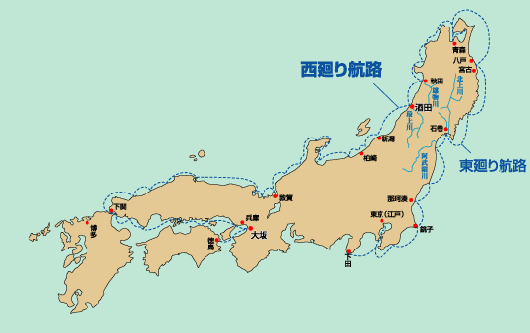 今のように鉄道や自動車など、陸の交通機関が発達していなかったころ、荷物を運ぶ手段は舟でした。江戸時代、幕府へ年貢米を回送するために、太平洋側を通る「東廻り航路」と、日本海側を通る「西廻り航路」が開かれました。この「西廻り航路」のおかげで、最上川は経済の大動脈として山形の発展を担いました。
今のように鉄道や自動車など、陸の交通機関が発達していなかったころ、荷物を運ぶ手段は舟でした。江戸時代、幕府へ年貢米を回送するために、太平洋側を通る「東廻り航路」と、日本海側を通る「西廻り航路」が開かれました。この「西廻り航路」のおかげで、最上川は経済の大動脈として山形の発展を担いました。
航路が整えられると、各川岸に船着場が設けられ、いろいろな荷物が運ばれるようになりました。
|
|
●関連事項/ |